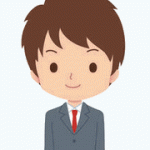ETC利用時のインボイス対応の基礎
ETCを利用した場合、利用時にはそのままゲートを通過しますので利用時に領収書や証明書を受け取ることはありません。
ETCの利用にさいしてクレジットカードを決済手段として利用する場合は、後日クレジットカード会社よりETCの利用明細が送られきます(もしくはクレジットカード発行会社のサイトからダウンロード出来るようになります)のでその金額をもとに会計ソフト入力などを行いますが、このクレジットカード会社から送られてくるETC利用明細はインボイスとして利用することができるのでしょうか。